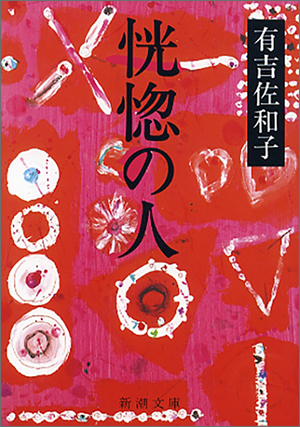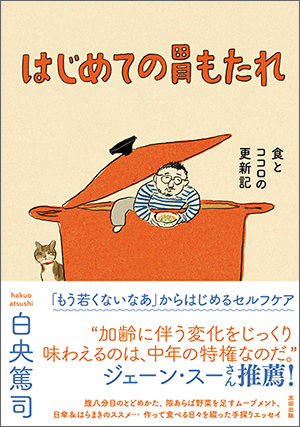老いについて
2025年05月22日 中村 発
中川さんが紹介してくださった縄文の動画とってもよかったです!
小学4年のときの担任の先生が新人のハリキリマンで、まさにみんなで縄文を再現しようと、木の棒に石をくくりつけて斧を作り校庭に穴を掘って火をおこし、クラスのみんなでカボチャを湯がいて食べた思い出がよみがえって、さっそくチャンネル登録いたしました(ホクホク)。
さてご多分に漏れずネタ切れで、当ブログの執筆者向けマニュアルに紹介されている「ブログネタ一覧まとめ」を久々に見に行ったら更新日がなんと2017年、「Twitterやってる?」などのネタがあり「Oh…」となりました。
そのブログネタ一覧の冒頭「未来・将来について」で思い当たることがあったので書きます。
昨年実家の父が米寿を迎え、奇しくも同じ年に喜寿を迎えた母がその世話にいろいろと困っているようなので、そういえば認知症を患う舅の世話に奔走する嫁の話があったなあと有吉佐和子のベストセラー「恍惚の人(新潮文庫/Amazon)」を読んでみました。
1972年の作品のせいか何でもかんでも嫁まかせで辟易しましたが、50年以上経った今でも大して変わっていないのかもしれません。舅の認知症はどんどん悪化し、徘徊や妄想、さまざまな異常行動が続きます。子どもに戻っていくお爺さんに振り回される家族には常に「自分もこうなるのだろうか?」という思いがつきまといます。
読んでいる間ずっと「ぐぬぬ」でしたが、時代のせいか言葉遣いが丁寧であったり、舞台が東京都杉並区で以前私も住んでいたことがあるし今も杉並区薬剤師会さんに仕事で関わっているため見慣れた地名の福祉施設を訪ね歩く嫁の姿がリアルで、何よりも有吉佐和子の「読ませ力」がすごくて引き込まれました。自分も妹たちと今後の親との関わり方を話し合わないといけないと思わされましたが、実際に顔を合わせると酔いに任せて笑える話しかしないので困りものです。
「自分の老い」については明るい気づきを得た本もありました。白央篤司「はじめての胃もたれ 食とココロの更新記(太田出版)」です。
「食べて書く」フードライターを生業とする著者がアラフィフになり、年々脂っこいものが苦手になったり、若い頃のように一日に何軒もラーメン屋を回って比較記事を書くことなどが段々できなくなったり、はじめての胃もたれを経験するのだけど、その一連の「歳を重ねたことによる変化」をポジティブに受け止め、加齢上等!華麗に加齢!とばかりに「年齢なりの豊かな食生活およびマインド」を工夫していく記録の本です。キッチリした分量や写真は載っていませんが、後期中年にも嬉しい料理がたくさん出てきます。
自分も胸焼けがひどくて先日とうとう「逆流性食道炎」という高齢者にありがちな診断名がついてしまったので、「うんうん、前みたいに食べられない!分かる!」とか「若いころは気付かなかったミョウガの美味しさ!分かる!」と我が意を得たりのガッツポーズ(古)をたびたび取りながら読みました。
さっきも一度出しましたが「豊かな」という表現がしっくりくる「これからの道」を歩いてゆきたいものです…。たとえば中川さんが同じ記事で紹介してくださった「発酵食品」なども「しっくり豊か」かもしれません(円環構造にしてみました笑)。
皆さまもどうぞご自愛くださいませ。